企業の基幹システムとして多くの企業に導入されている「SAP」は、実は「サップ」ではなく「エスエーピー」と読みます。ドイツ発のソフトウェア企業であるSAPの社名と、その代表的なERP(基幹システム)も同じく「SAP」という名称のため、「SAP=会社名、システム名」になります。
このsapですが、会計・生産・物流といった幅広い機能を一元管理するため、世界中の大企業が導入している一方で、日本では「使いづらい」「自由が利かない」という声が後を絶ちません。本記事では、SAPが「使いづらい」と感じられる理由と、グローバルで支持され続ける背景、日本企業の導入事例をご紹介します。
SAPシステムが使いづらい理由とは
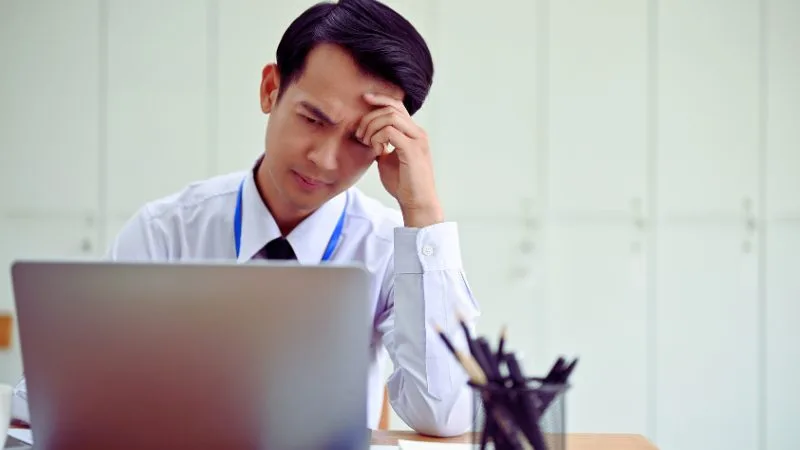
SAPシステムは、世界中の企業で利用されているERPソリューションの一つとして広く知られています。しかし、特に日本の企業においては「使いづらい」と感じられるケースが少なくありません。
その背景には、SAPシステムの設計思想やUI/UX、さらに日本特有の労働文化とのギャップが関係しています。本章では、SAPシステムが使いづらいとされる具体的な理由について詳しく解説していきます。
理由1:経営視点を重視した設計
SAPが「使いにくい」と感じられるのは、このシステムがもともと経営者や管理者の視点を重視して作られているからです。経営層は、全社の状況を正確な数字で、しかもリアルタイムに把握できるようになります。たとえば、在庫情報が入荷した瞬間に更新されれば、経営側は常に最新データをもとに意思決定が可能です。
ところが、そうした「理想的な情報環境」を支えるためには、現場が厳格なルールに従い、細かいデータ入力を続けなければなりません。簡単な修正でも承認が必要で、在庫と会計データを正確に紐づける手間が増えます。結果的に、現場は少しの変更にも時間や手間をかけざるを得ず、「自由が利かない」「操作がわずらわしい」という不満が積み重なります。
不正や改ざんを防ぎ、全社的な基準で統一管理を実現する仕組みも、現場には追加の作業をもたらします。必要な書類を添付し、すべてが整合するまで面倒な手順を踏む必要があり、業務が複雑化します。経営視点では望ましい状態ですが、現場にとっては「手間が増えるだけ」と感じられがちです。
結局、SAPの「使いにくさ」は、正確性と透明性を重視した全社最適化と、現場の負担増とのせめぎ合いにあります。使いやすさを優先すればデータの信頼性が下がり、経営判断に影響が出ます。逆に信頼性を高めれば、現場の作業が煩雑になります。SAPが使いにくいのは、経営者向けの最適化が、どうしても現場には重荷となる構造的な問題なのです。
しかし、UI/UXを改善すれば日常的なストレスや手間が軽減できるはずにもかかわらず、現状ではこの部分も非常に使いづらいと感じられています。ここからは、なぜUIやUXそのものが利用者に「わかりにくい」「扱いづらい」と思われているのか、その原因や背景について掘り下げていきましょう。
理由2:UI/UXの問題
現場ユーザーからは「SAPは使いづらい」という声が根強く存在します。この使いにくさの要因は、UX(ユーザーエクスペリエンス)およびUI(ユーザーインターフェース)の領域にも起因していると考えられます。
従来のSAP GUIは、複雑なメニュー階層や膨大な項目数、タブが乱立する画面設計など、直感的な操作を妨げる構造になっていました。近年、WebベースのSAP Fioriが導入され、操作環境は改善傾向にありますが、それでも画面のレスポンス低下や煩雑な手順が残存しており、初心者はもちろん、業務経験豊富なユーザーにとっても負担となっています。
たとえば、販売(SD)や購買(MM)モジュールでの伝票登録では、組織情報から多数の詳細項目まで、何度も画面を切り替えなければなりません。特定の処理を呼び出すために必要なトランザクションコード(Tコード)は、直感的な名称ではなく、一覧表を参照しながら操作する場面が多いです。
また、エラーメッセージが原因箇所を明確に示さないケースもあり、問題箇所の特定や修正に余計な手間がかかっています。会計(FI)モジュールについても、簿記の常識的な感覚とは異なる画面設計が見受けられ、標準画面を避けてExcelやCSVを用いるなど、現場で独自の工夫をおこなっていることが多いです。
さらに、SAPはドイツ発のソリューションであり、グローバル展開される中でローカライズ(各国語への翻訳や表記最適化)が不十分な部分が見受けられます。一部のエラーメッセージや画面上のラベルが直訳的であったり、業務用語として定着していない表現を含んだりすることが、ユーザー理解を妨げる一因となっています。こうした言語面の課題は、特に多文化・多言語環境での運用において顕在化しやすいです。
実際、日本のような独自で複雑な業務慣習を持つ環境下では、SAPのようなグローバルなシステムの標準機能だけでは運用が難しく、カスタマイズやアドオン開発による追加的な負担が常態化しがちです。
つまり、SAPが使いにくいという声が日本では多く上がっていますが、海外ではそのような声の表面化が少ないと言います。これはなぜでしょうか。日本特有の理由から、SAPの使いにくさの要因をご紹介します。
理由3:日本の労働文化と合わない
この背景には、グローバルで設計されたシステムと日本特有の業務文化や運用環境との間にあるギャップが挙げられます。日本の企業がSAPを使いこなす上で直面する具体的な課題を掘り下げるとともに、他国と比較してどのような違いがあるのでしょうか。
人材が変わらない
海外では、管理職と現場作業員の役割が明確に分かれており、管理職の権限が強いため、現場担当者がシステムを選ぶ権限を持つことは少なく、運用の円滑化が優先されます。たとえば、SAPに精通した人材を高給で採用するなど、人材の流動性を活用する仕組みが整っています。
一方、日本では、現場担当者が長期間にわたり同じ役割を担い、業務の安定性や深い知識を維持する文化があります。この強みが細やかな対応を可能にする一方、役割の交代が難しく、システム運用に柔軟性を欠く場面が生じることもあります。また、現場の「使いにくい」という声が表面化しやすい環境にあるため、海外とは異なる課題が浮き彫りになります。
これらの要因が、日本においてSAPの使いにくさを強調する背景と言えます。
業務フローの基準
日本と海外では、ERPシステム導入における基本的なアプローチに違いがあります。
多くの日本企業では、既存の業務プロセスや現場の慣習、日本独自のビジネス習慣があり、それにシステムを適応させる形で導入を進めることが傾向があります。そのため、ERPシステムの標準機能をそのまま利用するのではなく、多くの調整やアドオン開発が必要となり、結果的に運用が複雑化します。そのため、現場の負担が増加し、システム本来の効率性が発揮されにくいという課題があります。
一方、海外ではERPシステムの標準機能を基準として業務プロセスを見直し、システムに適応させる取り組みが一般的です。システムに業務を適応させるため、導入プロセスで大きな変革が求められますが、その分、運用がシンプルになり、システムの効果が最大化されます。
労働環境や業務に対する考え方
海外では、現場担当者とデータ入力担当者の役割が明確に分けられていることが一般的です。事務作業は専門の外部会社に委託したり、AIやIoTを活用して自動化するなどの対応も考えられており、現場作業者は本来の業務に集中できる環境が整えられています。
一方、日本では、現場作業者がデータ入力まで兼任することで、業務全体の一貫性を確保しやすい環境が特徴的です。現場の知識を活かしながらシステム運用を進めるため、業務の細部にまで注意が行き届く点は日本の強みと言えるでしょう。ただし、現場の人数を増やさずにシステム入力を担当させるケースが多いため、作業者への負荷が増大しやすい状況も見受けられます。
この労働環境の違いが、SAPシステムの使いづらさをより一層強調しています。
専門技術を持つ人材の不足
日本では、IoTやDXの設計に精通した専門人材が不足していることが根本的な問題として挙げられます。専門知識を持つ人材が不足しているため、システム導入や運用におけるトラブルへの対応が難しくなりがちです。実際、現場を深く理解し、動作を確認しながら問題を判断できる専門家がいなければ、適切な運用や管理を行うのは難しくなります。
さらに、このような場合のシステム導入時には、現場の意見や影響、作業負荷を十分に検証する必要がありますが、これらが軽視されるケースも少なくありません。その結果、現場担当者の負担が増え、SAPの運用が難しいと感じられる要因となっています。
それでもSAPシステムが世界中で利用されている理由

企業の業務管理システムの中で、SAPはその長い歴史と圧倒的な導入実績により、世界中で広く利用されています。SAPは、企業の効率化、グローバル展開、業務プロセスの最適化を支えるため、強力で柔軟なシステムを提供し続けています。
SAPの50年以上にわたる実績と信頼性
SAPは、50年以上にわたり業務管理システムを提供し、世界中の企業に不可欠な存在として位置付けられています。その導入実績は、190か国以上、44万社以上に達しており、この広範な実績がSAPの信頼性と効果を証明しています。多種多様な業種や地域にわたる導入事例は、SAPの柔軟性と適応力を示す重要な要素となっています。
特に、「フォーブス・グローバル2000」に掲載される企業の90%以上がSAPを採用しているという事実は、その普及度と信頼性の高さを物語っています。
大手企業においてSAPが選ばれ続ける理由は、単にシステムの機能性や効率性だけでなく、世界中の企業で蓄積された業務最適化のノウハウを基にした標準化されたモデルが提供されているからです。これにより、企業は効率的かつ効果的な業務フローが検討できます。
グローバルスタンダードなシステム
SAPは単なる業務システムにとどまらず、グローバルスタンダードな基盤を提供するため、世界中に展開する企業は業務を標準化することができます。企業が複数の国や地域に拠点を持つ場合、各拠点で異なる業務プロセスやシステムを使用していると、効率的な運営が難しくなります。
SAPの導入により、企業はこれらの業務プロセスを統一することができ、異なる文化や言語、法規制を持つ拠点間でも一貫した運営が可能になります。これにより、企業全体での業務の透明性が高まり、データの一元管理が実現します。
買収時におけるSAP導入の重要性
加えて、SAPは企業が持続的に成長するための基盤を提供するだけでなく、買収や統合の際にも重要な役割を果たしています。実際、SAPを導入していない企業が買収される際、システムの統合にかかるコストや時間が増加し、スムーズな業務の引き継ぎが難しくなるため、企業の価値が低下する可能性があります。買収元企業がすでにSAPを導入している場合、システムの統合がスムーズに進むため、企業価値を維持しやすいというメリットがあります。
このように、SAPは企業の成長、効率化、さらには競争力の強化を支える重要なシステムとして、世界中の企業に利用されています。
なぜ多くの日本企業がERP導入に失敗したのか

多くの日本企業がERP導入に挑戦したものの、その多くが期待した成果を得られずに失敗に終わりました。その背景には、ERPの本質に対する理解不足や、日本独特の文化や業務スタイルが深く関係しています。ERPは単なるシステムではなく、企業全体の業務を効率化し、経営の基盤を支えるためのツールです。では、なぜ日本企業はその恩恵を十分に活かすことができなかったのでしょうか?
導入失敗の理由
日本企業がERP導入に失敗した背景には、システムに対する理解不足や文化的な特性が深く影響しています。ERPは本来、会社全体の業務を効率化し、経営をサポートするツールです。
しかし、ERPが登場したばかりの当時の日本では、企業やITベンダーでさえもその価値を十分に理解せず、「新しいシステムを導入すること」が目的となり、どう活用するかが曖昧なまま進められました。
さらに、日本独特の現場主義も導入を難しくしました。長年にわたり現場で作り上げられた独自の業務プロセスを重視するあまり、ERPの標準機能を受け入れず、現場のやり方を維持するためにシステムを無理にカスタマイズしました。この過剰なカスタマイズは、導入にかかる費用や時間を大幅に増加させただけでなく、システムの運用を複雑化させ、期待通りの成果が得られない原因となりました。
また、日本の文化的な特徴として、業務の正確性や完璧さを求める傾向が強く、ERPのリアルタイム性や柔軟性を活かすことが難しかったことも失敗の一因です。例えば、欧米型のERPが目指す「大まかなデータ管理」ではなく、日本では「細部までミスなく処理すること」が優先され、これが現場に負担をかけ、導入がうまく進まない要因となりました。
さらに、ERPの導入には専門的な知識が必要ですが、当時の日本企業にはそうしたスキルを持つ人材がほとんどおらず、外部に頼らざるを得ない状況がありました。この外部依存が、システムが企業の実態に合わない結果を招くことも多かったのです。
結果的に、ERP導入は「経営を変革するツール」として期待されながらも、現場優先の対応に引っ張られ、「現場のためだけのシステム」として形骸化してしまうケースが目立ちました
SAPの導入失敗と成功:企業一例
企業がSAPを導入する背景や目的はさまざまですが、その結果が必ずしも成功に結びつくわけではありません。システムの選定や導入プロセスの問題により失敗に終わるケースもあれば、長期的な取り組みを通じて大きな成果を上げた事例もあります。
ブリヂストンやキリンホールディングスなどの成功事例と、ノーリツや江崎グリコといった課題を抱えた事例を紹介します。
株式会社ブリヂストン
株式会社ブリヂストンは、業務の拡大に伴い販売物流システムの処理能力が限界に達し、データを統合して業務効率を上げる必要に迫られていました。また、グローバル経営基盤を整え、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めることも重要な課題でした。
そこで、既に導入していた「SAP R/3」を販売物流システムにも拡大し、最新の「SAP S/4HANA」にアップグレードしました。このシステムは、既存の操作画面に合わせて構築され、全国50の販売会社や500の営業所にスムーズに導入されました。その結果、業務のデジタル化とデータの一元化を実現し、処理能力が向上したことで、事業拡大への対応力も強化されました。
さらに、「SAP S/4HANA」によってリアルタイムのデータ処理や高度な分析が可能になり、3,800人のユーザー、9つの製造拠点、8つの地域販売エリアをカバーするグローバル規模の運用を実現しました。導入時には専門コンサルタントの支援を受け、トラブルを最小限に抑える計画的な運用が行われました。
この取り組みによって、ブリヂストンは業務の効率化と柔軟性を高め、グローバルな市場変化にも迅速に対応できる基盤を構築しました。
ミドリ安全株式会社
ミドリ安全株式会社は、2020年3月にSAPジャパン株式会社の公式サイトで、最新ERP「SAP S/4HANA®」およびマネージドクラウドサービス「SAP HANA® Enterprise Cloud」の採用が発表されました。
その一方で、2023年9月25日に基幹システムの切り替えに伴うシステム障害が発生し、2024年2月15日に公式サイトでその状況が公表されています
⇒【公式】ミドリ安全株式会社:システム障害のお知らせはこちら
ただし、この基幹システム切り替えがSAPに関連するものかは明らかにされていません。その後、復旧に関する公式な発表も確認されていない状況です。
キリンホールディングス株式会社
キリンホールディングス株式会社は、2027年までに食品と医療の分野で新たな価値を生み出し、持続可能な成長を目指す計画を進めています。その一環として、経理、生産、物流の基幹業務を効率化するために、SAPシステムを導入し、業務プロセスの標準化を推進しています。
プロジェクトでは、従来分散していた事業部門ごとのシステムを統一し、クラウド環境へ移行することで、柔軟で効率的な業務運用を実現する狙いがあります。また、既存の事業領域で蓄積されたデータを活用し、さらなるデータ連携の強化や付加価値の創出にも取り組む予定です。
江崎グリコ株式会社
江崎グリコ株式会社は2019年12月、基幹システムをSAPの「SAP S/4HANA」に統合するプロジェクトを開始しました。約340億円を投じたとされるこのプロジェクトは、業務効率化とデータ活用を目指したものでしたが、2024年4月のシステム切り替え時に重大な障害が発生。物流業務の停止や主力商品の出荷停止など、大きな混乱を招きました。
影響は経営にも及び、2024年の第2四半期決算では売上高が150億円、営業利益が36億円押し下げられ、純利益は前年比53%減となりました。
その後復旧が進み、2024年11月には全品目の出荷を再開し、正常稼働に至っています。
⇒【公式】江崎グリコ株式会社:システム障害復旧のお知らせはこちら
今回の失敗は、CIO不在や段階的移行の欠如、計画遅延などの課題が原因とされ、ERP導入の難しさを浮き彫りにしました。この事例は、システム刷新プロジェクトの教訓として注目されています。
株式会社ノーリツ
株式会社ノーリツは1996年にSAPのERP「R/3」を導入するプロジェクトを開始し、4年をかけて2000年に完成。しかし、高額な保守費用やバージョンアップの追加コストが判明し、システムは稼働直後に廃棄され、16億円の特別損失を計上しました。この失敗の背景には、トヨタ流生産方式(JIT)とERPの主要機能(MRP)の不適合や、外付けシステムの多さによる運用コスト増加がありました。
システム廃棄後、ノーリツは「業務ありき」の姿勢に立ち返り、JITの再追求や原価低減を進め、2003年には過去最高益を達成。一方で、ERP導入は一部の成果を生み出しましたが、データ分散や運用の複雑さといった課題も残りました。これ以降、ノーリツはシステム導入に対して慎重な姿勢を取るようになりました。
まとめ
SAPシステムが「使いづらい」と感じられる背景には、経営視点を重視した設計や、UI/UXの複雑さ、日本特有の労働文化や業務スタイルとのギャップが挙げられます。これらの要因が、現場の作業効率や運用の柔軟性を阻害する結果となり、特に日本企業で課題として浮き彫りになっています。
しかし一方で、SAPはその信頼性とグローバル標準の仕組みを提供するシステムとして、多くの企業で必要不可欠な存在です。課題を乗り越えるためには、UIの改善や業務プロセスの見直し、専門人材の確保といった取り組みが欠かせません。システム導入時には、現場の声を取り入れながら、経営と現場のバランスを取るアプローチが求められるでしょう。



